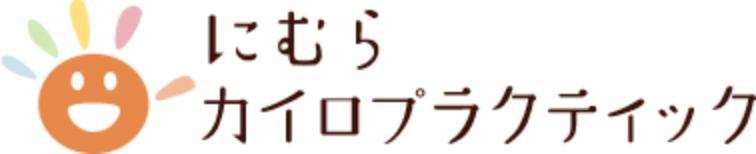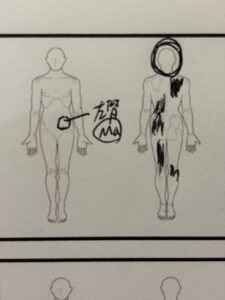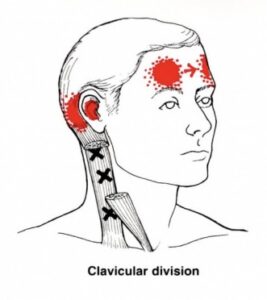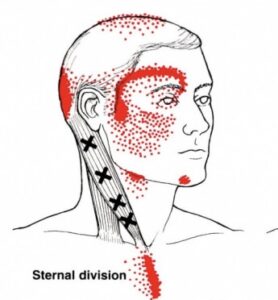大阪府東大阪市河内花園の【筋膜リリース整体院】にむらカイロプラクティックです(=゚ω゚)ノ
【症例】
60代 女性
【主訴】
左右に首を回せない、上を向く事が出来ない
【経緯】
定期メンテナンスの方
【施術内容】
首の可動域制限の要因としては、
①頚椎2番の関節が引っかかっている状態。
②頚椎2番に付着する筋肉による制限。
③上記①②の両方の問題。
①の場合は骨格矯正をするだけでOK。
今回のパターンは②の状態でした。
頚椎2番に付着する『頚長筋』『後頭下筋群』『肩甲下筋』を筋膜リリース。
【結果&まとめ】
勿論、可動域制限は全て回復(‘ω’)ノ
どの方向へも顔をスムーズに向ける事が出来ました(^^♪
今年は3月~5月の異常気象による自律神経ダメージの影響で体中の筋膜癒着は例年の2~3倍(;^ω^)
体調不良の方も多く、今迄経験した事のない症状が現れてお困りの方も多い事でしょう(‘ω’)ノ
最後に今回の筋膜癒着の写真をご覧ください(‘ω’)ノ